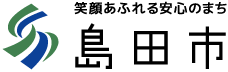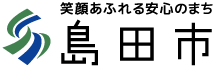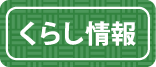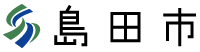償却資産の概要(令和7年11月28日更新)
- 「償却資産(固定資産税)申告書」はこちら
- 「償却資産の手引き」はこちら
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している方が、その固定資産が存在する市町村に納める税金です。
賦課期日
固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日に固定資産を所有している方にかかる税金で、例年5月初旬に納税通知書を発送し、年税額を4回に分けて納めていただいております。
年の途中で資産の売却や廃棄等をした場合であっても、1月1日現在の所有者がその年の納税義務を負うことになります。
納税義務者
固定資産税の納税義務者(税金を納める方)は、1月1日における固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
- 土地-登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
- 家屋-登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
- 償却資産-償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
償却資産とは
固定資産税の課税客体となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
土地及び家屋は、用途に関わらず所有していれば固定資産税が課税されますが、償却資産は事業に使用しているものに限って課税されます。
償却資産の要件
固定資産税の課税対象となる償却資産には、次のような要件が定められています。
- 固定資産税の土地及び家屋の課税客体ではないこと
- 無形減価償却資産ではないこと
- 税務会計上の損金又は必要な経費に算入されるべき性質の資産であること
- 税務会計上の少額減価償却資産ではないこと
- 自動車税又は軽自動車税の課税客体ではないこと
詳しくは「償却資産(固定資産税)の対象となる資産について」をご覧ください。
申告書の提出先
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日における償却資産の状況を1月末日までにその資産が所在する市町村に申告しなければなりません。そのため、複数の市町村に償却資産を所有する場合には、所在する市町村それぞれに償却資産申告書を提出する必要があります。
例えば、島田市外に本社がある法人であっても、島田市内の支店で償却資産を使用している場合又は、島田市内の事業者に償却資産を貸している場合には、島田市内に所在する償却資産については島田市に申告していただく必要があります。
税額算出方法
償却資産申告書により申告された資産一品ごとに、その取得価額、耐用年数及び経過年数に基づき、税金の元となる課税標準額を算出し、これに税率をかけることで固定資産税額を算出します。
詳しくは「税額の算出方法」をご覧ください。
税率
島田市の固定資産税の税率は1.4%です。
土地、家屋及び償却資産の課税標準額の合計額に1.4%をかけた金額に端数処理を行うことで税額を算出します。
免税点
償却資産の課税標準額の合計額が、免税点(150万円)に満たない場合、その年は、償却資産に固定資産税が課税されません。
例えば、償却資産の課税標準額の合計が120万円であった場合、免税点150万円に満たないため、その年は償却資産に固定資産税はかかりません。
申告の留意点
個人事業者の方が亡くなられた場合
年の途中で個人事業者が亡くなられた場合には、その年の税金は、相続権のある方が納める必要があります。
個人事業主が亡くなられて事業を廃止した場合は、お手数ですが相続権のある方が、事業を廃止した年月日や資産の処分状況等を記載した償却資産申告書を提出してください。
また、事業を相続(承継)された場合は、亡くなられた方の住所・氏名欄を二重線で消し、新たな所有者に書き換えた償却資産申告書を提出してください。
| 所有者 | 償却資産申告書の取扱い |
| 旧所有者(亡くなられた方) | 事業廃止として提出 |
| 新所有者(相続人・承継した方) | 事業開始(新規)として提出 |
事業を廃止した場合
年の途中で事業を廃止した場合であっても、その年の税金は納めていただく必要があります。
事業を廃止した場合は、事業を廃止した年月日や資産の処分状況等を記載した償却資産申告書を提出してください。
名称を変更した場合
事業者名を変更した場合には、旧名称と新名称がわかるよう住所・氏名欄を二重線で消し、新たな所有者に書き換えた償却資産申告書を提出してください。
ただし、新旧所有者の法人番号が異なる場合や法人成りした場合には、別の所有者として取り扱いますので、それぞれ償却資産申告書を提出する必要があります。
事業を一時休業した場合
事業を一時休業している場合であっても、使用できる状態で保管されている償却資産は、固定資産税の課税対象となりますので、償却資産申告書を提出する必要があります。
有姿除却した場合
使用してきた償却資産が、生産方式の変更、機能の劣化等の事由によって使用されなくなり、将来転用する見込みもなく、維持補修されないまま放置された状態にある場合、税務会計上有姿除却しているのであれば固定資産税は課税されませんので、償却資産申告書から除却してください。
償却済みの資産について
耐用年数を経過(償却済み)した償却資産であっても、事業に供している資産は固定資産税の課税対象となりますので、償却資産申告書に記載してください。
修繕した場合
償却資産の機能を維持するために支出された費用は、修繕費として税務会計上一時に損金又は必要な経費に算入され、固定資産税の対象から外れます。
改良した場合
償却資産の使用可能期間又は機能を増加させるために支出された費用は、改良費に該当し、固定資産税の課税対象となりますので、償却資産申告書に記載してください。
改良費は、機械設備本体の価額と区分し、改良費を一つの資産として申告してください。この場合の耐用年数は、機械設備本体の耐用年数と同じ年数とし、改良を加えた時期を取得時期とします。
申告誤りが見つかった場合
すでに提出した償却資産申告書に誤りが見つかった場合は、速やかに修正申告書を提出してください。
修正申告書の様式は、通常の償却資産申告書の様式と同じです。
修正申告をする場合、申告用紙の備考欄にその旨が分かるよう記載してください。
国税との違いについて
固定資産税の償却資産には、税務署に提出する減価償却資産と異なる点がありますのでご留意ください。
詳しくは「償却資産に対する固定資産税と国税との違い」をご覧ください。
償却資産(固定資産税)の対象となる資産について
| 資産種類 | 具体例 |
| 構築物及び附属設備 |
【構築物】 看板(広告塔等)、庭園、門、塀・緑化施設等の外構工事、フェンス、構内舗装(駐車場の舗装路面含む)、焼却炉、屋外配管、貯水池など
【附属設備】 受変電設備、生産事業(製造、加工、修理等)の工程上必要な設備(工場における動力用電気設備、製品の洗浄用・冷却用の給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備等)、中央監視制御設備、建物から独立した諸設備(スポットライト、外灯等)、テナントの内装工事など |
| 機械及び装置 |
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、印刷機械、農業用機械、太陽光発電設備など |
| 船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船など |
| 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
| 車両及び運搬具 |
大型特殊自動車が固定資産税償却資産の対象
|
| 工具器具及び備品 | パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機など |
| 業種等 | 具体例 |
| 各業種共通のもの | パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等(賃借人(テナント)等が取り付けた場合)、看板(広告塔、ネオンサイン等)など |
| 小売業 | 陳列棚、陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む)、間仕切など |
| 喫茶、飲食店 | カウンター、室内装飾品、放送設備、カラオケ機器、厨房設備、冷蔵庫など |
| 工場、作業所 | 受変電設備、旋盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、門、塀、溶接機、貯水設備、福利厚生設備、大型特殊自動車、看板など |
| 印刷業 | 各種製版機及び印刷機、断裁機など |
| 建設業 | 大型特殊自動車、ポンプ、発電機、コンクリートカッター、ミキサーなど |
| 理容、美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤー、サインポールなど |
| クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、給排水設備、ビニール梱包装置など |
| 病院、診療所 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、ベッド等)、各種キャビネットなど |
| 駐車場業 | 屋外照明設備、路面舗装、駐車装置、料金清算機、フェンスなど |
| ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、地下タンク、独立キャノピー、防壁など |
| 不動産賃貸業、ビル、アパート | 受変電設備、電気設備、屋外の給排水ガス設備、駐車場等舗装路面、植込み、看板、通信放送機器、中央監視制御装置、集合郵便受け、フェンスなど |
| パチンコ店 | パチンコ・パチスロ台、両替機、玉貸機、還元機、駐車場設備、照明設備など |
| ホテル、旅館業 | 客室設備、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、駐車場設備など |
| テニスクラブ | コート、フェンス、オートテニス設備、人工芝、駐車場設備、照明設備など |
| ゴルフ練習場 | フェンス、ネット設備、芝刈機、ボール自動貸出機、集球設備、照明設備など |
| カラオケボックス | カラオケセット、接客用家具、駐車場設備、照明設備など |
| コンビニエンスストア | 陳列台、冷蔵・冷凍ショーケース、温熱ケース、カウンター、電子レンジ、事務所の事務機器、駐車場等舗装路面、周囲の塀・側溝など |
| 農業 | ビニールハウス、資材置き場、脱穀機、籾摺り機、乾燥機、大型特殊自動車など |
テナントが取りつけた内装、造作は、テナントが償却資産として申告してください。
上の表はあくまでも参考であり、必ずしもこの例示によらない場合があります。
少額の減価償却資産の取扱い
| 償却方法 | 取得価額 | ||||
| 10万円未満 |
10万円以上 20万円未満 |
20万円以上 30万円未満 |
30万円以上 | ||
| 1 | 一時に損金算入(1)(5) | 対象外 | - | - | - |
| 2 | 3年で一括償却(2)(5) | 対象外 | 対象外 | - | - |
| 3 | リース資産(ファイナンスリース)(3) | 対象外 | 対象外 | 対 象 | 対 象 |
| 4 | 中小企業者等の少額資産特例(4)(5) | 対 象 | 対 象 | 対 象 | - |
| 5 | 個別に減価償却しているもの | 対 象 | 対 象 | 対 象 | 対 象 |
(1)法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により、損金算入する取得価額が10万円未満の資産又は使用可能な期間が1年未満の資産は対象外です。個人の方については、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した10万円未満の資産は全て必要経費となり、個別に減価償却することはないため対象外です。
(2)取得価額が20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択した場合、対象外です(一括償却)。
(3)平成20年4月1日以降、法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で、取得価額が20万円未満のものは課税対象になりません。
(4)青色申告書を提出する中小企業等が、租税特別措置法第28条の2、第67条の5を適用して取得した30万円未満の資産は、損金算入(即時償却)が認められますが、固定資産税では課税対象になりますので、償却資産の申告が必要です。
(5)上記表中の1、2、4の償却方法について、令和4年4月1日以降に取得し、貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供する資産は当該償却方法の対象外です。
賃借人(テナント)が施工した内装等について
賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方(テナントといいます。)が、内装や電気・ガスその他の設備一式を施工されている場合、それらの資産は、テナントが償却資産として申告してください。
| 内装 | 天井、床、内部・外部仕上げ、建具、間仕切り、その他工事 |
| 附帯設備 | 電気・ガス・給排水・衛生・空調・運搬設備、その他設備 |
割賦販売、リース資産について
割賦販売により購入した資産については、所有権が売主に留保されている場合であっても、買主が申告することになります。
リース資産(ファイナンスリース)については、通常、リース会社からの申告となりますが、譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売に相当するものなど、賃借人が申告をする必要があるものがありますので、取扱いが不明な場合は契約書をご確認ください。
無形減価資産償却資産の取扱い
無形減価償却資産は、その資産が具体的に存在するものではない等の理由から、固定資産税が課税されません。
無形減価償却資産は、固定資産税償却資産申告書に記載しないでください。
|
農業用資産について
農業を事業として行っている方が、その事業のために用いる機械、器具は、固定資産税の対象です。
該当する資産を所有する方は、毎年1月末日までに償却資産申告書を提出してください。
| 資産の種類 | 主な資産の例 |
| 構築物 | ビニールハウス、物置、ごみ置き場等 |
| 農機具 | 脱穀機、籾摺り機、乾燥機等 |
| 車両 |
大型特殊車両 (農耕作業用車両で最高時速35km以上のもの) |
太陽光発電設備について
事業者が所有されている太陽光発電設備又は、個人が所有されている太陽光発電設備のうち売電方法が全量売電となっているものは、固定資産税の対象です。該当する資産を所有する方は、毎年1月末日までに償却資産申告書を提出してください。
| 設置者 | 売電方法 | 固定資産税 | 申告対象となる資産 |
| 個人(住宅用) | 余剰売電 | 対象外 | なし |
| 全量売電 | 対象 |
太陽光パネル、架台、送電設備、 電力量計、パワーコンディショナーなど |
|
| 個人事業者及び法人 | 余剰売電 | ||
| 全量売電 |
ただし、屋根一体型の太陽光発電施設で固定資産税の家屋の評価に含まれ、家屋として課税される太陽光パネルは、償却資産申告書に記載しないでください。
車両の取扱い
車両のうち固定資産税 償却資産の課税対象となるのは大型特殊自動車のみです。
自動車税又は軽自動車税の課税対象となる車両は、固定資産税の対象外となるため、償却資産申告書に記載しないようご注意ください。
| 税区分 | 車両区分 | 種別 | 大きさ | 最高速度 |
|
軽自動車税の対象 (固定資産税の対象外) |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 制限なし | 35km/h未満 |
| その他 |
長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下 |
15km/h以下 | ||
| 固定資産税の対象 | 大型特殊自動車 | 小型特殊自動車の要件に当てはまらないもの | ||
遊休又は未稼働の資産
メンテナンス等を行い使用できる状態にある遊休資産や使用予定のある未稼働資産は、その資産が事業の用に供することができる状態にあるものとして申告対象になります。
福利厚生用資産
福利厚生用の資産は、本来の事業の用に直接供されてはいませんが、更衣室のロッカー、社員食堂の厨房設備等は、事業を行うのに必要なものとして申告の対象になります。
美術品等
「美術品等」とは、絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当します。
取得価額が1点100万円未満のものについては、減価償却資産に該当します。
ただし、1点100万円未満の美術品等であっても、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかな資産であれば、減価償却資産としては取り扱われません。
また、逆に100万円以上の美術品であっても、会館のロビーや葬祭場のホール等不特定多数の方が利用する場所の装飾用や展示用として使用するもののうち、移設することが困難なもの、かつ、他の用途に転用したとしても美術品等としての市場価値が見込まれないものについては、時の経過によってその価値が減少することが明らかなものとして減価償却資産として取り扱われます。
償却資産に該当しない資産
次の資産は固定資産税償却資産に該当しないため、償却資産申告書に記載しないでください。
-
固定資産税の家屋として課税されるもの
-
自動車税又は軽自動車税が課税される車両
-
「車両の取扱い」はこちら
-
-
無形資産(例:特許、漁業権、プログラムソフトなど)
-
「無形減価償却資産の取扱い」はこちら
-
-
繰延資産(創立費、開業費、開発費、社債発行費等)
-
取得価格が10万円未満で一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの
-
取得価格が20万円未満で財務会計上3年間で一括償却しているもの
-
「少額の資産の取扱い」はこちら
-
-
売買扱いとするファイナンスリース資産で取得価格が20万円未満のもの
特例資産について
償却資産の中には、法令の定めにより固定資産税の課税標準額を減額できる特例の適用を受けるものがあります。
特例の適用を受ける資産を購入した場合、該当する資産であることを証明する書類を添付し、償却資産申告書及び種類別明細書に、特例を特定できるよう特例の名称及び税法の条項番号を記載してください。
主な特例は、次の表のとおりです。
| 地方税法附則 | 固定資産の種類 | 特例率 | 適用期間 | 添付書類 |
|
第15条第25項第1号イ |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電1,000kw未満) ・令和6年4月1日~令和8年3月31日までに取得 |
3分の2 | 3年間 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金 交付決定通知書等 |
|
(旧) 第15条第44項(賃上げ表明有り) |
中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の設備等 ・令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得 |
3分の1 |
4年間 |
先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し、先端設備等導入計画に係る投資計画に関する認定書(認定経営革新支援機関確認書)の写し、先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新支援機関確認書)の写し、従業員の賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(※賃上げしない場合は不要) |
|
(旧) 第15条第44項(賃上げ表明無し) |
中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の設備等 ・令和5年4月1日~令和7年3月31日までに取得 |
2分の1 | 3年間 | |
|
第15条第43項(賃上げ目標3%以上) |
中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の設備等 ・令和7年4月1日~令和9年3月31日までに取得 |
4分の1 | 5年間 | |
| 第15条第43項(賃上げ目標1.5%以上) |
中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の設備等 ・令和7年4月1日~令和9年3月31日までに取得 |
2分の1 | 3年間 |
償却資産に対する固定資産税と国税との違い
- 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、旧定率法です。
- 取得価額は、原則として国税の取扱いと同じです。
- 固定資産税では、圧縮記帳は認められていません。国庫補助金等で取得した償却資産で取得価格を圧縮したものについては、圧縮前の取得価格を記入してください。
- 減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数表に応じて定められています。
| 項目 | 固定資産税 | 国税(所得税、法人税) |
| 償却計算の基準日 |
1月1日(賦課期日) |
事業年度 |
| 減価償却の方法 |
定率法(法人税法等の旧定率法で用いる償却率と同様) |
建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度 |
| 前年中の新規取得資産 | 半年償却(2分の1減価率) | 月割償却 |
| 圧縮記帳 | 認められません | 認められます |
| 特別償却・割増償却 | 認められません | 認められます |
| 増加償却 | 認められます | 認められます |
| 評価額の最低限度額 | 取得価額の5% | 備忘価額(1円) |
| 改良費(資本的支出) | 区分評価 | 原則区分評価 |
|
中小企業者等の少額償却資産の損金算入(租税特別措置法) |
認められません | 認められます |
税額の算出方法
評価額の計算
償却資産の評価額は、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。
評価額が取得価格の5%になるまで、毎年、減価償却します。
具体的には、前年の評価額に減価残存率を掛けたものがその年の評価額となります。
ただし、課税1年目(その資産が初めて課税される年)については、その資産を取得した月に関わらず半年償却します。
1年目の評価額=取得価格×1年目の減価残存率
2年目以降の評価額=前年の評価額×2年目以降の減価残存率
資産の耐用年数に応じた減価残存率が定められています。
課税標準額の計算
評価額に特例割合を掛けた額を課税標準額といいます。
特例の適用を受けない資産については、評価額と課税標準額は同額です。
評価額×特例率=課税標準額
固定資産税額の計算
課税標準額に税率1.4%を掛けた額が税額です。
課税標準額×税率1.4%=固定資産税額
税額の算出例
エアコンを例に税額を算出してみます。
エアコンの詳細
- 取得価格700,000円
- 耐用年数6年
- 特例の適用なし
課税1年目の税額
- 取得価格700,000円×1年目の減価残存率0.840=評価額588,000円
- 特例の適用なし
- 課税標準額588,000円
- 課税標準額588,000円×税率1.4%=固定資産税額8,232円
課税2年目の税額
- 前年の評価額588,000円×2年目以降の減価残存率0.681=評価額400,428円
- 特例の適用なし
- 課税標準額400,428円
- 課税標準額400,428円×税率1.4%=固定資産税額5,605円
課税3年目以降の税額
課税2年目の計算と同じように、前年の評価額に減価残存率と税率を掛けることで、固定資産税額を算出することができます。
償却資産(固定資産税)申告書
償却資産申告書・種類別明細書.pdf (PDF 220KB)
償却資産申告の手引き