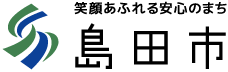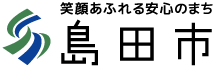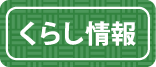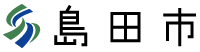高齢者虐待とは、高齢者の心や体に深い傷を負わせる、財産を不当に処分する、基本的な人権の侵害や尊厳を奪うなどの行為をいいます。
このような行為に対応するため、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」という。)が平成18年4月1日に施行されました。
高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、速やかに市町村に通報する義務があると定められています(高齢者虐待防止法第7条)。虐待や虐待の疑いがあると気づいたときには、早めに相談・通報することで事態の深刻化を防ぐことができます。
高齢者虐待の区分
高齢者虐待防止法では高齢者虐待を「養護者(現に高齢者を養護する者)による高齢者虐待」、及び「養介護施設従事者等による高齢者虐待」に分けて定義しており、次のような行為が虐待にあたります。
身体的虐待
殴る・蹴る・物を投げる等の身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある行為
ベッドに縛りつけたり、部屋に閉じ込めたりするなど
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
食事をさせない、入浴をさせない、おむつ交換をしない、劣悪な環境で生活させるなど
高齢者に必要な介護や医療のサービスを制限するなど
心理的虐待
怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視をする、侮辱を込めて扱うなど
排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話したりするなどの高齢者に恥をかかせるなど
性的虐待
わいせつな行為をする、性的行為を強要するなど
排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置するなど
経済的虐待
日常生活に必要なお金を渡さない、使わせないなど
年金や預貯金を勝手に使うなど
高齢者虐待を防ぐために
虐待は家族等(養護者)がしようとして発生しているものだけではなく、高齢者のことを思っての介護がいつの間にか不適切な介護になっており、意図せずして虐待になってしまっていることもあります。
高齢者虐待を防ぐためには、介護している家族等(養護者)や高齢者を地域で見守るなど、孤立させないことが大切です。
また、社会的なサービスを効果的に利用するなど、介護している家族等(養護者)の負担軽減や、無理をせず心身ともに余裕をもって介護を継続することができる環境をつくることが重要です。
高齢者虐待に関する相談窓口
高齢者に関する虐待の通報、虐待疑いにかかる相談、介護のご相談はお住まいの地域を担当する高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)にご連絡ください。
お住いの地域を担当する高齢者あんしんセンター(中学校区ごとに設置されています)