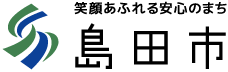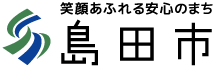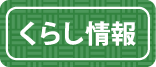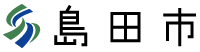個人の市民税・県民税
個人の市民税・県民税は、その年の1月1日現在市内在住の人に対し、前年の所得を基礎に課税されます。
個人の市民税・県民税には所得割と均等割があります。
所得割は所得に応じ、均等割は限度額(扶養無の場合、38万円)を超える所得があれば課税されます。(令和4年6月17日更新)
ただし、生活保護法によって生活扶助を受けている人など、非課税の規定により課税されない場合もあります。
課税通知と納期
市民税・県民税の課税通知は、個人が直接納付する普通徴収の場合は、6月中旬頃、個人宛に送付します。
また、給与支払者(事業所など)が、市役所からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き納入している特別徴収の場合は、5月中旬頃に給与支払者を通して通知します。
普通徴収の納期は6月・8月・10月・翌年1月の4回、特別徴収の納期は6月分から翌年5月分までの12回です。
市民税・県民税の給与所得に係る特別徴収(給与引き去り)について
市民税・県民税の『特別徴収』とは、給与支払者である事業所など(特別徴収義務者)が給与所得者である従業員(納税義務者)に対して毎月支払う給与から、個人の市民税・県民税額を天引きし、従業員に代わって市に納入する制度です。
詳しくは→『市民税・県民税』の特別徴収(給与引き去り)について(島田市ホームページ)
市民税・県民税の税率(令和6年5月14日更新)
- 市民税所得割税率:6%
- 県民税所得割税率:4%
- 均等割税額:4,400円(市民税:3,000円、県民税:1,400円) (注1)
- 森林環境税(国税):1,000円 (注2)
注1:令和7年度まで森林(もり)づくり県民税400円を含みます。
注2:市民税・県民税の均等割は東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていましたが、この臨時措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が賦課徴収されることとなりました。
詳しくは→森林環境税について(島田市ホームページ)
年度の途中で住所が変わった場合(令和7年5月2日更新)
市民税・県民税はその年の1月1日に住んでいた市町村が課税することになっています。
例えば、令和7年1月1日現在島田市に住んでいた方が、令和7年4月1日に他の市町村に転出した場合、令和7年度の市民税・県民税は島田市が課税します。
市民税・県民税の申告書作成や税額試算をしたい場合(令和7年12月26日更新)
住民税試算システムに、給与や年金収入、所得控除などを入力することで、市民税・県民税の申請書作成や税額の試算をすることができます。
詳しくは→【住民税試算システム】市民税・県民税の申告書作成と税額試算ができます!(島田市ホームページ・別ウィンドウで開きます。)
また、市民税・県民税の電子申告について、詳しくは→個人住民税(市民税・県民税)申告の電子化について(令和8年度分申告から)(島田市ホームページ・別ウィンドウで開きます)
マイナンバーカードを使って税情報を確認したい場合(令和6年9月13日更新)
マイナポータル内の「わたしの情報」から申請を行うことで、個人住民税情報を確認することができます。
「わたしの情報」を確認するには、マイナンバーカードを読み取った上で、利用者登録/ログインが必要です。
マイナポータル「わたしの情報」について(外部サイト・別ウィンドウで開きます。)
1 確認できる内容
・ご本人の所得及び個人住民税に関する情報を取得できます。
・「課税」か「非課税」かの情報について、確認できます。また、自己責任でダウンロード(保存)することができます。
※印刷も可能ですが、公共の証明書としては使用できませんのでご注意ください。
2 必要なもの
・マイナンバーカード(暗証番号が必要です。)
・マイナンバーカード読み取りが可能なスマートフォン
・(上記スマートフォンがない場合)パソコンとマイナンバーカード対応したICカードリーダライタ
3 注意事項
・「わたしの情報」から確認できる所得及び個人住民税に関する情報は例年7月頃までに更新されます。
・未申告の場合は情報がありませんので、税情報等を取得する場合には申告が必要です。
・住民税課税情報に変更があった場合などは、反映までに時間がかかることがあります。
マイナポータルの利用方法については、以下のリンク先をご覧ください。
【マイナポータル:操作マニュアル (わたしの情報)】
01 わたしの情報を取得する(外部サイト・別ウィンドウで開きます)
02 わたしの情報の回答結果を確認する(外部サイト・別ウィンドウで開きます)
市民税・県民税・森林環境税の減免について(令和7年11月13日更新)
下記の事由により、市民税・県民税・森林環境税を納めることが困難である場合は、申請により税額を減免できる場合があります。
- 生活保護の受給のため
- 災害による被害のため
- 収入の著しい減少のため(※)
- 勤労学生のため
※収入金額が生活保護基準に相当するかどうかを照らし合わせ、貯金や資産の有無を含め総合的に審査します。
申請を希望される場合は、下記フォームに入力するか課税課(0547-36-7140)へ電話にてお問い合わせください。
市民税・県民税・森林環境税 減免申請相談フォーム
「ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度」について
自分の応援したい市町村(※)に2,000円を超えて寄附金を納めた場合、所得税及び個人市県民税が一定額控除される制度です。
※平成31年度税制改正により地方税法が改正され、総務省が定める基準に適合する都道府県・市区町村に対し寄附金を支出した場合に限り、この税額控除が適用されることとなりました。
この改正は、令和元年6月1日以降に支出する寄付金について適用されます。(平成31年4月25日更新)
関連ページ(令和3年10月1日更新)
- 「ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度」について(島田市ホームページ)
- 静岡県が条例で定める寄附金について(島田市については静岡県と同じです。)(静岡県ホームページ・別ウインドウで開きます。)
- 住民税試算システム(ふるさと納税限度額の試算ができます。)(島田市ホームページ・別ウィンドウで開きます。)
上場株式等に係る配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について
令和6年度(令和5年分)から
株式等に係る譲渡所得及び上場株式等に係る配当所得(源泉徴収を選択した特定口座内のもの)について、所得税と市民税・県民税とで、異なる課税方式を選択することが可能とされてきましたが、令和5年分(令和6年度)から課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。【令和4年度改正】
令和5年度(令和4年分)まで
平成29年度税制改正により、株式等に係る譲渡所得及び上場株式等に係る配当所得(源泉徴収を選択した特定口座内のもの)について、所得税と住民税(市民税・県民税)とで、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。(例:所得税では申告分離課税、住民税では申告不要制度など)
課税方式
- 上場株式等に係る配当所得等
- 総合課税
- 申告分離課税
- 申告しない(申告不要制度)
- 株式等に係る譲渡所得
- 申告分離課税
- 申告しない(申告不要制度)
申告の方法
納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、「市民税・県民税申告書」を提出することによって、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株 式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合 (所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、所得税の確定申告書第2表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の 申告不要」欄に○を記入することでも申告できます。(この場合、その申告内容から変更がなければ、市民税・県民税申告書を改めて提出する必要はありません。)(令和4年6月17日更新)
注意点
- 「市民税・県民税申告書」の提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が選択されたとみなします。
- 納税通知書が送達された後に提出された所得税の確定申告書によって、異なる課税方式を選択しても、市民税・県民税の課税方式は変更されません。
- 申告不要を選択できる所得について、市民税・県民税において総合課税や申告分離課税を選択した場合、配当割額や株式等譲渡所得割額の控除等を受けることができますが、その所得は合計所得金額に算入されます。
- 合計所得に算入されることで、市民税・県民税の非課税判定や、扶養控除の判定のほか、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などに影響が出る場合があります。
関連ページ
- 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)(国税庁ホームページ・別ウインドウで開きます。)
- 上場株式等の配当所得等に係る申告分離課税制度(国税庁ホームページ・別ウインドウで開きます。)
退職所得に係る市民税・県民税
退職所得に係る市民税・県民税については、原則として退職所得の発生した年に他の所得と区分して納税義務者のその年の1月1日現在の住所地の市町村に課税されます。
納付については退職金の支払者が特別徴収します。
退職所得の金額
(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額
- 勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数
- 勤続年数が20年を越える場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※障害退職の場合は100万円加算されます。(令和4年6月17日追加)
1/2課税の適用について(令和4年6月17日追加)
- 従業員
- 勤続年数5年以下
- 退職所得控除後の額の300万円以下の部分:1/2課税適用あり
- 退職所得控除後の額の300万円超の部分:1/2課税適用なし
- 勤続年数5年超:1/2課税適用あり
- 勤続年数5年以下
- 役員
- 勤続年数5年以下:1/2課税適用なし
- 勤続年数5年超:1/2課税適用あり
国税に関する相談相続税・贈与税の事業承継税制度については、国税庁ホームページ(外部サイト・別ウィンドウで開きます。)をご覧ください。