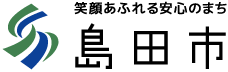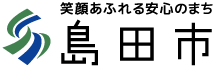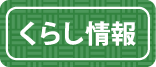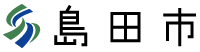平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
1.施設の移行
平成27年3月以前の幼稚園、認定こども園、保育所は平成27年4月より原則新制度に対応することになりました。
| 新制度に移行する幼稚園 | 旧制度のまま継続する幼稚園 | |
|---|---|---|
| 認定区分 | 必要(1号認定) | 不要 |
| 保育料 | 市が保護者の所得状況に応じて定める | 各幼稚園が独自に定める |
関連リンク
2.認定区分と利用可能な施設・事業
新制度では、幼稚園・保育所・認定こども園・小規模保育事業施設を利用する場合、子どもの年齢・保育の必要性に応じた認定を受ける必要があります。→「認定証」を交付します。
2号認定・3号認定は、保育の必要量によって「保育標準時間」と「保育短時間」に分けられます。
| 保育を必要としない | 保育を必要とする | |||
|---|---|---|---|---|
| 認定区分 | 教育・保育の必要量 | 認定区分 | 教育・保育の必要量 | |
| 3歳以上の子ども | 1号認定 | 教育標準時間 | 2号認定 | 保育標準時間 保育短時間 |
| 3歳未満の子ども | - | - | 3号認定 | 保育標準時間 保育短時間 |
| 施設・事業 | 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | |
|---|---|---|---|---|
| 教育・保育施設 | 認定こども園 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 幼稚園(※) | 〇 | |||
| 保育園 | 〇 | 〇 | ||
| 地域型保育事業 | 家庭的保育 | 〇 | ||
| 小規模保育 | 〇 | |||
| 居宅訪問型保育 |
|
〇 | ||
| 事業所内保育 | 〇 |
原則、認定区分に応じて〇印の施設・事業の利用が可能です。
新制度に移行しない幼稚園を利用する場合、認定は不要です。
3.保育を必要とする事由
保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、家庭で子どもを保育することができない場合、保育所等を利用することができます。(2号認定または3号認定に該当)
- 就労することを常態としていること
- 妊娠中又は出産後間がないこと
- 疾病、負傷又は障害を有していること
- 同居の親族(長期間入院をしている親族を含む)を常時介護又は看護していること
- 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっていること
- 求職活動を継続的に行っていること
- 就学していること(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められること
- 児童虐待を行っている又は行われるおそれがあると認められること
- 育児休業するとき既に保育を利用している子どもの継続利用が必要であると認められること
4.教育・保育の必要量
新制度では、保護者の就労状況等に応じた「教育・保育の必要量」の認定が新たに導入されました。
幼稚園の利用を想定した「教育標準時間」、フルタイムの就労を想定した「保育標準時間」、パートタイムの就労を想定した「保育短時間」が認定されます。
- 教育標準時間・・・1日4時間程度の利用
- 保育標準時間・・・1日最大11時間の利用(月120時間以上の就労時間で検討中)
- 保育短時間・・・・・1日最大8時間の利用(月64時間から月120時間未満の就労時間で検討中)
5.利用手続きの手順
旧制度のまま継続する幼稚園の利用を希望する場合
- 保護者が、幼稚園に直接申込を行います。
- 幼稚園から入園の内定を受けます。
- 保護者と幼稚園が契約をします。
新制度に移行する幼稚園等の利用を希望する場合(1号認定)
- 保護者が、幼稚園等に直接申し込みを行います。
- 幼稚園等から入園の内定を受けます。
- 保護者は、幼稚園等を通じて市へ認定申請を行います。
- 幼稚園等を通じて、市から認定証が交付されます。(1号認定)
- 保護者と幼稚園等が契約をします。
保育所等の利用を希望する場合(2号認定・3号認定)
- 保護者が、市に「保育の必要性」の認定申請を行います。
- 市から保護者へ認定証が交付されます。(2号認定・3号認定)
- 保護者が、市に保育所等の利用希望の申し込みを行います。
- 保育所等の状況、保護者の希望等により、市が利用調整をします。
- 保育所等の決定後、利用契約をします。
※1と3の申し込みは同時にできます。
6.保育料について
保育所・認定こども園・新制度に移行する幼稚園(認定証を必要とする施設)
保育料は、国で定める基準を上限として、市で基準を設定します。認定区分ごと、保育標準時間・保育短時間別の保育料体系となり、保護者の所得状況に応じた設定となります。
保育所の保育料は市、認定こども園・幼稚園の保育料は各施設に納付します。
旧制度のまま継続する幼稚園
保育料は、現在と同様に各幼稚園が決定します。
幼稚園の保育料は、各施設に納付します。